こんにちは。出世魚のごとく製図から開発まで行った氷河期の住人だよ。
製図、設計、開発、研究・・・
ひとえに製造業の図面を扱う職種といっても色々あるわけですが、これらの違いがわかりますか?
今回は業界20年、製図から研究開発まで経験した私が、これらの違いとどういったことが求められるか実体験からまとめてみました。
これを知っておくと、キャリアアップをするにはどういったことを学ばないといけないのかがわかるようになると思います。
先に結論だけ書きますと、それぞれこんな感じの仕事です。
| 分類 | 仕事内容 | 必要なもの |
| 製図 | 製造に指示を出す仕事 | 加工・組立・部品の知識 |
| 設計 | 計算する仕事 | 力学や材料学、ありとあらゆる計算知識 |
| 開発 | 仕様を決める仕事 | ミスター味っ子並みの創意工夫 |
| 研究 | うまくいくかどうかを試す仕事 | 特定の分野の高度な知識 |
では、詳細な内容に触れていきたいと思います。
製図、設計、開発、研究の違いを知ろう!
目次(クリックできるよ!)
ちなみに製図、設計、開発、研究の順番ですが、右にいくほど価値の高い業務になります。
製図
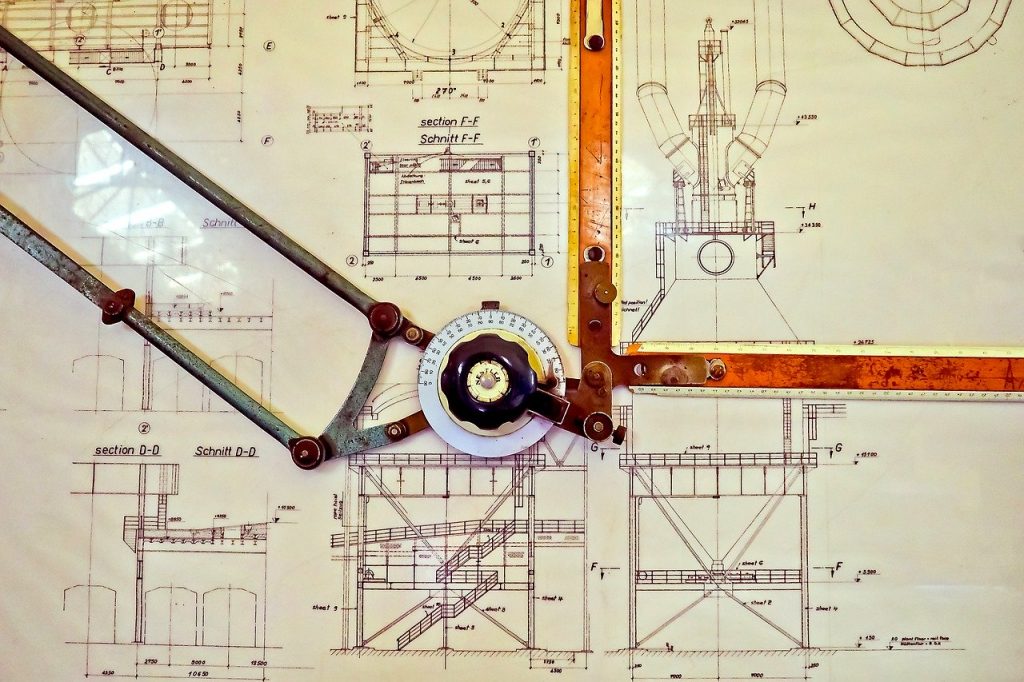
製図というのは「図面を書く」ものです。でも実際にはそれだけではないので、拡大解釈すると「製造部署に指示を出す」と言えます。その手段のひとつが「図面を書く」です。
製図の業務とは?
製図の業務は、名前の通り図面を書くことです。図面によって、加工や組立部署に指示を出すことになります。
これだけで終わればいいのですが、実際は加工や組立から問い合わせが来ますので、それに対応することもあります。また、「こう直してくれ」という製造要望を織り込んで改訂をすることもあります。
製図に必要な知識・技能
図面の書き方
まず知識として必要なのは、やはり図面の書き方です。機械系では寸法の入れ方や溶接指示などはできないと仕事になりません。
電気系では電源系統の回路の組み方だったり、センサなど購入品とコントローラを結線する方法がわからないと図面が書けません。
加工方法・能力の把握、組立の知識
その次に必要なのは、加工や組立に関する知識です。加工や組立できないものは図面を書いてもしょうがないですから、当然ですね。
機械系だとフライス盤、マシニングセンタや溶接、電気系なら配線加工とか、電子系なら基板の製作方法などです。
加工や組立方法を知っておくと、コストダウンを考えられるようになります。
CAD
技能はやはりCADの操作です。CADができないと、何も始まりません。機械系ですと今時は3D-CADが主流ですので、最低限3D-CADのモデリングと製図操作ができなくてはいけません。
電気・電子系でも同じです。回路図はCADで書きますし、基板のパターンもCADで書きます。
製図に求められること
製図のアウトプットは、基本的に図面です。でも本当に求められているのは下の2つです。
どこに出しても同じものが出来てくる図面
製造工程がスムーズに流れることが、製図に求められることです。
設計
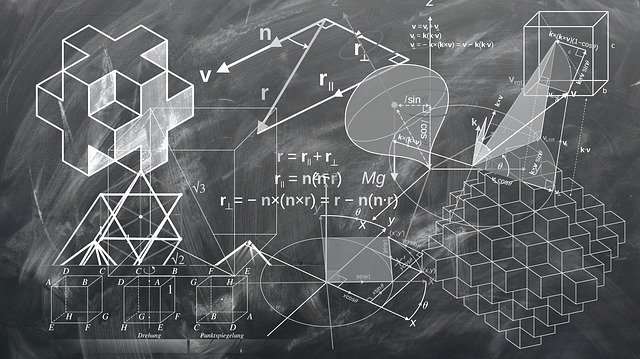
設計というのは、製図をするイメージが強いですよね。でも実際には、製図とは明確に違うことがあります。
設計に必要な知識・技能
製図の知識に加え、仕様・構造が成立するための計算をする能力が必要です。
電気の図面が書けても、実際は電流が低すぎて信号がノイズに負けた・・・
なんてことがあります。
トライ&エラーで失敗しながら作ればいいや、は昭和の発想です。
計算して作らないと、後々に重大な不具合を世に出すことになります。そうならないように計算をしまくるのが設計の仕事です。
設計に求められること
計算力もさることながら、購入品なども含めた部品に関する知識がないと設計はできません。
モータやシリンダ、センサなどの知識も必要です。そして、これらを選定するための計算も求められます。
資格取得・就転職を目指す方のための総合専門校「ヒューマンアカデミー」
開発

開発の仕事っていうと、花形なイメージです。でも実際は非常に地味なことの積み重ねだったりします。
仕様を決めて、製品化するのが開発の業務です。
開発に必要な知識・技能
設計製図の知識
設計製図の知識は最低限必要・・・といいたいところですが、大企業の開発者って製図できない人がけっこういます。なので、製図はできなくてもいいのかもしれません。
ただし中小企業では製図までできないとお話になりません。だれも替わりに図面を書いてくれる人がいないからです・・・。

知識の引き出しの多さ
開発に所属すると、様々な開発案件をやることになると思います。そのときに私が大事だと思うのが、分野を問わずいろんな知識を持っておくことです。
こんな知識何に使うんだ?という知識でも、意外に役に立つことがあります。私の特殊車両で得た知識が、全く別分野の現職にだって活かせています。
とある素材の話ですが、半年くらいかけて試行錯誤していた人から「なんかいい素材を知らない?」と聞かれたので「それなら・・・」と即答したら、なんとそれが上手くいったらしくて大変喜ばれました。
Point!その業界の常識は、その他の業界の非常識だったりします。
どんな経験でも役に立つものですので、引き出しを多く持っておくことを意識するといい開発ができます。
方法論や手法
QCって聞いたことありますか?Quarity Control、品質管理手法です。
こんな感じで世の中にはTQM、VE、FMEA、QFD、PMBOKなど無数の手法があります。

DAIGOさんかどうかは知りませんが・・・なんでだろう。
この中で確実に知っておきたいのはQCとVEです。
QC7つ道具の中ではパレート図と特性要因図、それ以外では「なぜなぜ分析」です。
間違いだらけの『なぜなぜ分析』から卒業!例題を交えた簡単なやり方
VEは開発の場合、ファンクショナルアプローチだけでも知っておくと仕事の質が一気に上がります。
コストダウンは『機能』がカギ!ファンクショナルアプローチ入門
開発に求められるもの
「ミスター味っ子」並みの創意工夫が求められます。

「ミスター味っ子」のあらすじ
簡単に「ミスター味っ子」について説明しますと、父の跡を継いで食堂を営む15歳の少年である味吉陽一が、料理界の強敵たちと対決するマンガです。
基本的にいつも味っ子は経験や素材で不利な状況なのですが、皆が度肝を抜かれるような創意工夫で強敵を撃破していくというのが最高に面白いのです。

・・・でもこれって、製造業の開発でも全く同じことをやってるんですね。
中小企業はリソースに限界があるので、かなりの創意工夫をしないと競合に勝てないのです。そういうところが、このマンガそのままなんです。
なので知恵を絞ったり、アイデアを出す練習をしっかりしておきましょう!
ビジネスマンは大喜利をやれ!?良いアイデアを出す『頭のひねり方』
研究

研究って、研究所にこもってるイメージだよね。実際そうです。成功するかどうかわからないものを何年もかけてやる、非常に根気強い仕事です。
研究に必要な知識・技能
特定の分野での高度な知識が必要です。そしてそれ以外はなくてもいい、という世界です。
育成ゲームでいうと、特定のパラメータに全振りした人っていうとわかりやすいかもしれません。私の知ってる研究職の人は、だいたいそんな感じです。
私が関わってる研究は言えないので例をあげると、ひたすら何十年もカップラーメンの麺だけを研究してる感じです。

とにかく長いスパンで新しいものを生み出す(できるかどうかはわからない)のです。ちなみに私が関わってた研究の最長が15年です。(最初の1年で辞めましたが、15年後に研究者の方と偶然再会して聞いたところ)
私はその間に3回転職しましたが。

研究に求められるもの
不屈の精神力と我慢強さです。
例えるなら、麻酔無しで親知らずを抜くくらいの精神力です。
私はこれがないので、もう研究はやらないのです。

上手くいくかわからないものを、いつまでもやるのは私の性格的に向いてないのです。
おわりに
ここまで読んで頂き、ありがとうございました。
キャリアプランの参考になれば幸いです。
私はFラン大ですし精神力もないので研究に向いてません。なので開発者として創意工夫の日々です。自分に向いている業務だと、やりがいも感じやすいですよ。
もし設計製図をやっている方、開発なんていかがですか?
それではまた。
