こんにちは、自発的に動きすぎて怒られっぱなしの氷河期の住人だよ。
あなたの会社は、指示待ち人間だらけですか?

約10社の職場で働きましたが、不思議なもので自発的に動く人が多い会社とそうでない会社って、けっこうはっきり分かれているものです。
今回はこんなお話です。
- 人はどうするとモチベーションが上がるの?
- 自発的に社員が動くために、どんな取り組みをしているか?
結論からいうと、これらが効果的なようです。
2.成長を実感してもらう
3.ニンジンをぶら下げる
自発的(能動的)に動く社員って、どうやったら育つ?
目次(クリックできるよ!)
理論の話と実際の取り組みをまとめてみました。
モチベーション理論

まずは理屈のお話です。偉い人が昔から研究してくれてるんですね。
マズローの要求段階説
人間の欲求が5段階ある、という説です。

2.安全の欲求(健康でいたい、など)
3.所属と愛の欲求(いい会社に入りたい、など)
4.尊重の欲求(尊敬されたい、など)
5.自己実現の欲求(想像する自分になりたい)
1~4までは欠乏動機といって、自分以外のもので満たされる欲求だよ。
5の自己実現の欲求こそが、人間らしいハイクラスな欲求で、満たされると更に強く求めるものなんだよ。つまり、もしこの欲求を社員が満たすことができたら、更に強く求めようとするので自発的に動く社員になるんだろうね。

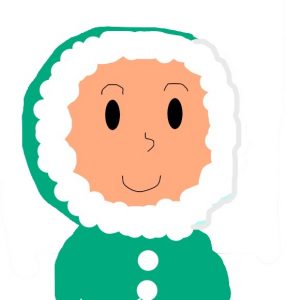
さて、ここからいろんな人がモチベーションに関する説や理論を展開しますが、本題から外れるので要点だけサラっと紹介します。
マクレランドの三欲求理論
社会人には3つの欲求があるということだね。
〇 権力欲求:ほかの人をコントロールしたいという欲求
〇 親和欲求:有効な人間関係を築きたい欲求

内発的・外発的動機づけ理論
内発的動機づけ要因は、報酬などとは関係なく自分の内部から引き出すものです。
〇 仕事をこなすことで得られる「有能感」(自分はできるんだ、という感覚)
〇 自分でやることを決められる「自立性」
一方、外発的動機づけ要因は給料や昇進・昇格などですね。我々はだいたいこれで働いています。
・・もうお気づきかと思いますが、外発的動機づけの場合は、報酬や昇進が無くなったり頭打ちになると、一気にモチベーションが低下します。
内発的動機づけはあくまで自分から出てくるものなので、上司がうまくフォローしてあげることで部下はモチベーションを保ち、自発的に仕事に取組み続けることができます。
モチベーション理論をまとめると
〇 社会人には達成欲求、権力欲求、親和欲求があるよ
〇 内発的動機づけと外発的動機づけ要因があるが、内発的動機づけは自分から出てくるものである
会社は実際にどんな取り組みをしている?
ここからは私の経験に基づいたお話です。
裁量を増やす

ある程度「おまかせ」することで裁量を増やす
これは多くの会社で見られます。私もよくやりますが、個々の社員にある程度任せてしまうということです。
さすがに1年目の社員に「あとはおまかせするね」というわけにはいきませんので、2~3年目の社員に初期段階の構想からやってもらってます。
開発職の場合で書いてますが、そうでない場合も、それまでの仕事よりも広範囲の業務であるほうがいいです。(「職務拡大」といって、単調な業務を紛らわす効果があります)
よほど無茶苦茶でない限りは若手社員の考えたことを否定せず、問題が起きても自分なりの解決方法を考えてもらうのが大事です。
こうしていくうちに、自然と自発的に動ける社員になっていることが多いです。

小集団活動で裁量を増やす
もう一つは新しく集団を作って、その中で裁量を与えるパターンです。
実際にやった例ですが、「職場の5Sプロジェクト」とか立ち上げて、そのプロジェクトメンバーがメンバー外の人に指示する権限を与えました。
すると普段は受け身がちだったメンバーが自発的に行動するようになり、思った以上の成果が出たということがありました。
思うに、これは三欲求理論の「権力欲求」を満たした結果なのかな、と思います。
裁量を増やす場合の注意点
自発的に仕事ができるようになってくれると非常にうれしいものですが、注意も必要です。
〇 人に指示するのが好きでない人もいるので、適正を見極める
成長を実感してもらう

「俺はできるんだ!」という気持ちになると、自発的にいろいろやりたくなりますよね。
(社内では)未知の技術を習得してもらって「専門家」になってもらう
実はこれ、内容が面白ければ内発的動機づけの全てが凝縮された方法です。しかも私の知る限り、非常に効果の高い方法です。
例えば社内では未知の技術が”Cのプログラミング”だとすると、ひたすらプログラミングを習得してもらいます。
社内の人は誰もCのプログラミングを知らないなら、自分でどうやって習得できるか考えないといけません。ここで「自立性」によって動機づけされます。
そして危なっかしいながらも製品に搭載できるレベルになってくると、立派な「専門家」です。そうなると「有能感」「満足感」が得られ、今度は他の人に指示することで「権力欲求」も満たされます。
そうなってくるとプログラミングを自分の専門分野として、自発的に成長をしてくれるようになっていきます。
ただ注意しないといけないことがありますよ。
〇 周りに自分の領域を知る人がいない場合、手を抜いてもバレないと思うようになるので注意する
ニンジンをぶら下げる

外発的動機づけ、要するにモノで釣るわけです。一時的な効果は内発的動機づけより上ですが、デメリットもあります。
報奨金制度
多くの会社で採用されている制度です。特許1件〇〇円、改善案1件〇〇円とかいうやつです。
私も特許を出すたびにいくらかもらっていますが、いいお小遣いになるので「年1件は出しときたいな」って思います。これでけっこうモチベーションが上がる人もいます。
しかしこの制度、問題点が2つあります。
〇 件数を稼ぐためにクオリティの低いものを乱発されがち
実際に改善案などで読む気が失せるようなものを乱発され、審査する手間ばかりかかってしまうというケースがありました。
昇進・昇格
どの会社にもある制度ですね。役職が上がったりすることで動機づけされる場合もあります。
しかし昇進・昇格も問題があります。
〇 部下の面倒を見るのが苦手な人には逆効果
〇 名プレーヤーは必ずしも名マネージャーではないので、会社としてマイナスになる場合がある
会社での取り組みについてまとめると
ここまでまとめます。
外発的動機づけをしても限定的な効果しかない場合が多いので、内発的な動機づけを与えるほうがいい
【まとめ】自発的に仕事をする社員を育てるには
ということで、ここまで3つご紹介しました。職場や部下に合ったやり方でモチベーションの高い職場を作りましょう!
〇 成長を実感してもらおう
〇 ニンジンで釣ろう
おわりに
ここまで読んで頂き、ありがとうございました。
今回モチベーション理論を調べてみて、今まで見てきた会社の制度が割と的を得ているんだなと思い、興味深くまとめることができました。
会社のモチベーションを上げたいかた、なんとなく伝わったでしょうか?

